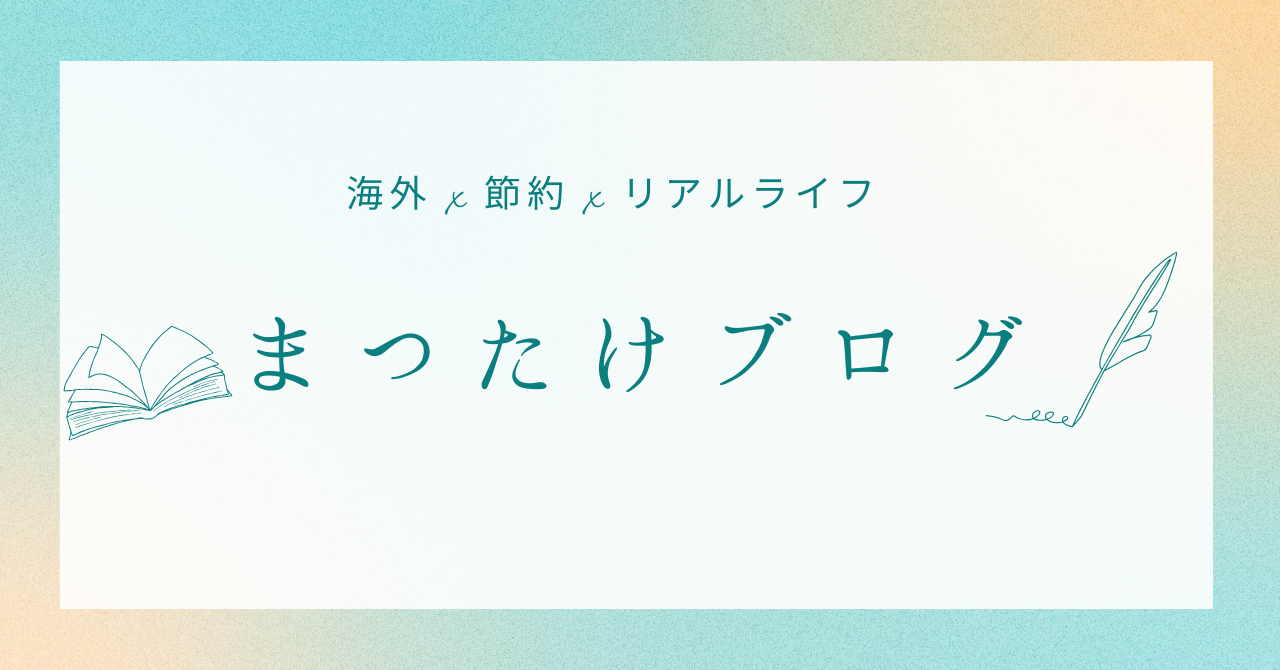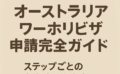2004年。
まだスマホもLINEもなく、SNSもmixiがようやく流行り始めた頃。
ワーホリの情報はネットよりも人づてと紙が中心だった。
そんな時代に、僕はオーストラリアに飛んだ。
今みたいに「#ワーホリ準備」も「英語学習アプリ」もなかったけど、
そのぶん、“生きる実感”は濃かった気がする。
出発のきっかけ:すべてお任せの某有名(当時)エージェントL(仮名)
ワーホリの準備は、当時から有名だった留学エージェントL(仮名)にお願いした。
ビザの取り方も航空券の手配も、正直なにもわからなかった。
でも担当の人が全部やってくれて、「ここにサインしてください」で終わり。
「英語も話せない、地理もわからない。でもなんとかなる」
そんな根拠のない自信でチケットを握っていた。
今思えば片道切符で当時で10万5000円も取られたのを覚えていて
ぼっ○くリ○ートなんて揶揄されてました笑
振り返ればいい思い出ですが航空券の手配なんて自分で楽勝にできるのにね。
これからワーホリを計画している人はエージェントに頼りたいところをグッと堪えてVISAと航空券くらいは自分で絶対に手配しましょう笑
浮いたお金はワーホリ初期の落ち着かない頃の生活費に当てた方が絶対に良いです!
それにしても今思えば、怖いくらい何も知らなかった。
スマホがないから空港の乗り換えもすべて紙のチケットと案内放送頼り。
飛行機の中で「オーストラリアって右側通行だっけ?」って本気で考えてた。
ホームステイ生活:当たりホストに救われた日々
最初の5週間は、ベクスリー(Bexley)という静かな住宅街でホームステイ。
子どもがいる家庭は苦手だったので、夫婦二人と犬2匹の家を希望した。
その希望が通って、若い夫婦+犬の落ち着いた家に決まった。


この子たちがその家のアイドル。
朝はいつも俺の部屋の前で尻尾を振って待っていて、
ホームシックになりかけたときも、こいつらの存在にどれだけ救われたか。
ホームステイには当たり外れがあるけど、
僕のところは**料理がうまくて、ルールがゆるい“当たりホスト”**だった。
「シャワーは5分まで!」みたいな制限もなく、
ご飯は手作りのローストチキンやパスタが多かった。ワインも飲ませてくれたし最高だった!
「お前、食べるの好きだな!」
と笑いながらおかわりをくれるホストファザー。
あの笑顔とあの味は、今でも忘れられない。
1週間300ドル。
今考えればあり得ない安さ。
でも当時の俺には、それでも結構ギリギリの出費だった。
語学学校の現実:真面目すぎた俺と、遊びモードのクラスメイト
ホームステイ後、4週間だけ語学学校に通うことにした。
「まずは英語力!」と思って、かなり真面目な気持ちで入学。
ところがクラスの雰囲気はまるで違った。
僕のクラスはintermediate.
クラスメイトはタイ、中国、韓国とアジア人が多かったかな。そこはチェコ人(当時)が唯一ヨーロピアンだった。
でも休み時間の話題は「今週末どこ行く?」「どのバーが安い?」ばかり。
最初は笑って合わせてたけど、心のどこかで温度差を感じ始めた。
「なんでみんな遊びに来てるんだ?」←今思えばそれくらいの話はするでしょ?笑
「俺はもっと真剣にやりたかったのに…」←みんな真剣だっただろうに、僕だけやる気の空回り笑
でもなんとなくその雰囲気に馴染めなかった僕は
3週目には気づけば足が遠のいて、4週で退学。
“ワーホリ=語学学校”のテンプレを踏んで、
僕は早くも“現地で働く方向”に舵を切った。
働くことで見えた、リアルなオーストラリア
語学学校を辞めたあと、仕事探しに切り替えた。
求人ももちろんネットじゃなくて掲示板の張り紙。
当時は「日豪プレス」や「CHEERS」みたいな情報誌をチェックしてた。
ネットにも情報はあったがネットもエージェントやネカフェに行かないといけない時代でした。
「ホールスタッフ募集」「キッチンハンド求む」
携帯はプリペイド式でガラケー、メッセージも文字数制限あり。
“即電話・即現場”が当たり前だった。
初めて働いたレストランでの英語は、
「Yes」「No」「Finished」「OK」だけでなんとかなってた。
でも、働くうちに自然と耳が慣れてきて、
“あ、俺、生きてるな”って感じた瞬間があった。
あの頃の不便さが、今の俺を作った
2004年のワーホリは、今よりずっと不便で、孤独で、アナログだったな。
でもそのぶん、人と関わる濃さが全然違った。
ホストファミリーとの食卓、(スマホを見ながら食事なんてことはないから話すしかない)
カフェで地図を広げる時間、(見知らぬ人が「どこへいくんだ?」なんて話しかけてくれたし)
日本に国際電話をかける緊張感。(公衆電話へいって、国際電話カードの番号を入力してやっと繋がる不便さ)
いまの便利なワーホリもいいけど、
あの頃の“何もない中でどうにかする感覚”は、
一生の財産になったと思う。
まとめ:不便だったけど、それも全部ワーホリだった
2004年のワーホリは、今よりずっと不便だった。
地図はプリントアウト、連絡は家の電話かガラケー、行き違いなんて日常茶飯事。
でもそのぶん、人に話しかける勇気が自然とついた。
わからないことは聞く、失敗したら笑う。
それだけでなんとかなる世界だった。
英語が通じなくて落ち込んだ日も、
ホストファミリーの犬が足にすり寄ってきて救われたこともあった。
完璧じゃない日々の積み重ねが、
いつの間にか「生きる力」になってた気がする。
便利な時代になっても、
ワーホリの本質ってそこまで変わってないと思う。
不安でも、準備不足でも、
とりあえず行ってみる。
その一歩の先で、何かが変わる。
それが2004年の俺が学んだ、ワーホリのいちばんの教訓だったかなぁ。
これからワーホリの計画をしてる人、絶対に行った方がいい!
いい経験もそうでない経験もすると思うけど、どちらも未来の自分の栄養になるから。